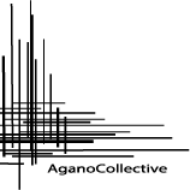少し前の話ですが、4月に新潟県議会において、原発再稼働問う県民投票の条例案が否決されました。
市の議員という立場ですが、このことについてちょっと考えさせられました。
今回は、知事も議会も総合的な判断が必要であるとして、反対だったとのことです。
県民投票については、新潟県の有権者の50分の1を超える署名、数にして約3万6千が必要で、それでもって直接請求というかたちで条例制定が可能となります。今回の署名数は14万筆という数の署名だったということから、どれだけ関心が高いかがわかります。
知事は、県民に信を問う、と再稼働について言及していましたが、県民投票には否定的な立場でした。国のエネルギー政策等々を理由にしていた訳です。
県議会では、否決となりました。間接民主主義が云々とか、国策が云々とか、県議会最大会派である自民党の議員からは、そういったコメントがありました。
住民投票というと、かつての旧巻町での原発をめぐる住民投票を思い出します。1996年に原発推進の是非を問う住民投票が実施されました。日本で初めての住民投票でしたし、町長、町議会でのやりとりがいろいろとあって、議会に住民が押し寄せたりと、ちょっとした騒ぎでした。推進派、反対派で町が分断されるようなことがあったようです。88%もの高い投票率というほとんどの有権者が意見を表明した結果は、建設反対が上回り、建設計画は取り下げられました。
https://ja.wikipedia.org/wiki/巻町における原子力発電所の建設に関する住民投票
住民投票がいいか、わるいか。首長と、議会の役割と機能。間接民主主義と二元代表制の意味。とても、難しいことですが、考えさせられます。今回の県議会の判断は、この旧巻町の原発建設の住民投票の影響が大きく、その傷、その痛みのようなものを思い起こされたのではないでしょうか。
今日は、7月14日で、参院選の真っ只中です。自民党が不利というふうに言われています。昨年の裏金問題のダメージも回復できないまま、今回の住民投票否決は、県議会最大会派である自民党は、我々の声を聞く耳すら持たない、というイメージを与えたように、私には思えます。
選挙の結果については、国民の総意である、わけですから、結果は、結果であります。結局のところ、国民の思い、というのが一番であるというのが、大事なんだろうと思うわけです。
ポピュリズムとか、極右とか、いろいろと言われているところですが、参院選の結果に注目したいと思います。