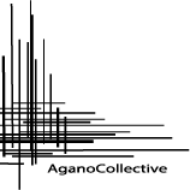昨日はあがの市民病院の会議でした。その前日に県知事とJA厚生連の会議があったばかりで、その直後ということだけあって少しだけピリっとする中での開催でした。
第三者委員として、自分も含め三名が参加。みなさん私と同様に新人議員で、市と病院と自己紹介からはじまりました。
私自身、かつてJAの理事をしていたこともあり、他人事とは思えない、今回の事態。というのは、昨年に発表されたJA厚生連の病院の経営危機、そして改善計画をするもなおも公的支援が必要と、県にお願いして、所在地の自治体から支援を県に要望するという一昨日までの流れがありました。県立病院においても赤字経営が懸念されており、緊縮財政の新潟県もギリギリのところなわけです。しかし、地域医療そのものの存続が危ぶまれる状況の中、県も支援を決定し、とりあえずは胸をなでおろしているというところでしょうか。
地域医療の危機ということがずっと言われていたところですが、どちらかというと医師不足という、あくまで供給側の問題でしたが、コロナ禍を経て状況は一変したようです。以前からの人口減少に加え、受診控え、医療費負担の増もあってか、受診行動の変化が大きいようです。
実はコロナ前から、収入減という状況はあったようです。そこにコロナで、ワクチンやら、補助金やらで、うやむやにされていたところ、コロナ終息と同時に浮き彫りになったようです。
あがの市民病院は、以前の水原郷病院の時から、いろいろな問題があったわけで、あがの市民病院を建てて、JA厚生連が運営して、一旦は安定していたような具合でした。それでも、救急告示がどうとか、市の負担がどうとか、診療科の減少とか、というのはあったわけですが、どれも今回の件に比べれば、ということです。
阿賀野市社会福祉協議会の理事もしてたんです。ちょうど市からの指定管理の介護のデイサービス事業所をいくつか閉鎖するという、なんとも悪いタイミングでした。もともと市というか、合併前の旧町村で、社協に委託したものでした。介護福祉サービスができて、民間でもサービス提供できているということで、ある意味では社協でサービスを提供する役割が終わったとも解釈できるのかもしれません。しかし、高齢者にとってデイサービスという社会参加の機会が減るというのは、いいわけはないのであって、しかも高齢化社会に向けてその事業者を失うのは市としても痛手なわけです。
当時、社協の職員に事業計画について、お話しする機会をいただきました。みなさん、まじめで一生懸命に取り組んでいるのは分かるのですが、どうもちょっとしたズレのようなものを感じました。顧客満足、というのが言われるようになって久しいのですが、ユーザーとしての高齢者というイメージがすでにズレてしまっているようなのです。本来であれば、いわゆるペルソナみたいなものがあって、サービスを考えると思うのですが、そこが固着してしまっていて、なかなかそのイメージから抜け出せないという印象を受けました。今回の病院においても、同じようなことが起こっているような気がします。
会議では、現在の病院の状況と次年度に向けての計画の説明がありました。経営改善に向けてのいい話が聞けたと思いますが、いかんせんふんわりとした感じを受けました。ちょっと細かいところまでは初回ということもあり、詰められなかったので、次回以降その成果に期待しつつ、しっかりと発言していきたいと思います。